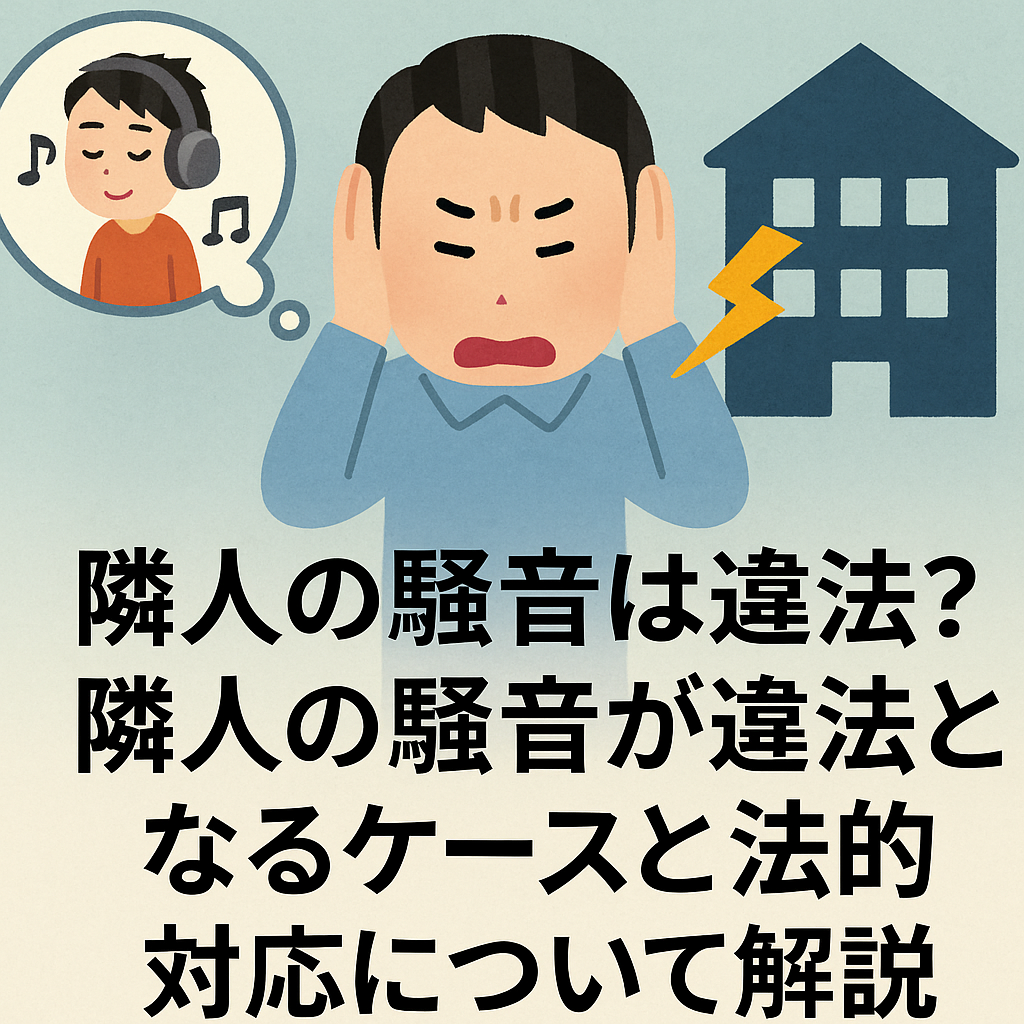
はじめに
隣人の深夜や早朝の騒音に悩まされていませんか?
騒音がひどいと精神的な負担が大きいですが、どこからが違法な騒音とされるのか線引きが難しいものです。
そこで、この記事では、隣人の騒音はどこからが違法な騒音なのかや、隣人の騒音に対する対応策について判例を交えて解説します。
「隣人の騒音」についての裁判例を紹介
まず、隣人の騒音を理由に損害賠償請求がなされた裁判例を紹介します。
歌声による深夜騒音(東京地判平成26.3.25)
東京都の分譲マンションで、7階に住む被告の深夜の歌声(最大41 dB)が上階に伝わり、受忍限度を超える騒音として損害賠償が認められました。損害賠償額は合計約40万に上りました(弁護士費用含む)。ただし、本判例では、差止請求は棄却されました。
幼児の飛び跳ね音(東京地判平成24.3.15)
マンションで上階の子どもの飛び跳ね音が室内に響き、その音が受忍限度を超えるとして損害賠償請求が認められました。騒音の数値は53dBを超えると判断され、子どもの親に対し、差止めと慰謝料が認められました。損害賠償額は夫が約94万円、妻が約32万円に上りました。
保育園における騒音(神戸地判平成29.2.9)
保育園の近くに居住する住民が、保育園の園児の声がうるさいとして損害賠償及び騒音対策を求めた事案です。本判決では、園児の騒音は基準値を上回っていました。しかし、園児が遊んでいる昼間の時間の等価騒音レベルに引き直して計算すると基準値を下回っていることや、保育園と自宅の距離などが考慮され、請求が棄却されました。
参考:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86519
判例を踏まえた隣人の騒音の「受忍限度」の判断基準
隣人の騒音が違法であるか否かを決するうえで基盤となるのが「受忍限度」です。
この受忍限度を超えていると判断されれば、原則として隣人の騒音が違法と評価されます。
最高裁平成6年3月24日判決では、受忍限度を超えているかの判断にあたって、以下の複数要素を総合的に考慮すべきと判断されました。
- 侵害行為の態様
- 侵害の程度
- 被侵害利益の性質
- 地域環境
- 持続・頻度
- 騒音防止措置の有無・内容
この判例を踏まえると、騒音に関する規制基準を超過しているからといって、必ずしも受忍限度を超えているとは判断されることにはなりません。
規制基準の超過はあくまでも考慮要素の一つに過ぎない点に注意が必要です。
実際に、上記の保育園における騒音が問題となった事案では、園児の騒音は基準値を超えているものの、保育園から自宅の距離が離れていること、騒音の時間帯や騒音対策を講じていることから、受忍限度を超えていないと判断されています。
最高裁平成6年3月24日判決:http://最高裁平成6年3月24日判決
隣人の騒音が発生した際の証拠の収集方法
隣人との騒音トラブルで裁判なった場合、勝敗を分けるのは、どれだけ客観的な証拠を揃えられるかです。
単なる「うるさい」という主観的な主張だけでは、裁判所に違法性を認めてもらうことは困難です。
そこで、以下で隣人の騒音が発生した際の証拠の収集方法について解説します。
騒音測定値の記録
まずは、市販の騒音計やスマートフォンアプリを用いて、dB(デシベル)値を複数回測定しましょう。
上記で解説したように、騒音の違法性が争われた判例では、デシベルの値を重要な考慮要素としています。
また、裁判例では、騒音の発生の時間帯も考慮要素としているため、測定は昼間・夜間に分けて行い、日時を明記するようにしましょう。
騒音による損害額を具体化する
隣人の騒音による損害額を具体化することも重要です。例えば騒音によって睡眠障害・ストレス・頭痛・体調悪化などが生じた場合、医師の診断書を取得することにより具体的な損害の証拠となります。
隣人の騒音による損害賠償を請求する場合は、損害の発生や騒音と損害の因果関係について、請求する側が立証する必要があるため、損害額を具体的に現す証拠が重要になります。
騒音に関する近隣住民の証言
自分だけでなく、複数人が被害を受けていることを示せば、受忍限度を超えていると判断されやすくなります。
そこで、あらかじめ近隣住民に騒音について相談することも有用です。
隣人の騒音に対する法的対応
以下では、隣人の騒音が気になる場合の法的対応について解説します。
管理会社や町内会に報告する
隣人の騒音が気になる場合には、まず集合住宅であれば管理会社、戸建てであれば町内会といった地域住民で組織された組合に騒音を報告しましょう。
管理会社や町内会にもよりますが、騒音を発している隣人に管理会社や町内会から注意をしてくれる場合があります。
内容証明を送付する
管理会社や町内会に報告しても改善されない場合、騒音を発している隣人に、騒音の原因となっている行為をやめるようにしてほしいという旨の内容証明を送付することが有用です。
内容証明では、単なるクレームではなく、日時・音量・継続性などと言った具体的な騒音の中身を明記しましょう。
さらに「判例上、受忍限度を超える場合は損害賠償が認められている」などと言った法的な対応も辞さない旨の文言を書き添えると説得力が増します。
調停・訴訟に踏み込む
隣人に内容証明を送付しても騒音が改善されない場合、調停や訴訟に踏み込むことも考えられます。
請求内容としては、騒音の差止めるように求める請求や、騒音によって生じた損害についての損害賠償請求が考えられます。
調停や訴訟に発展した場合は、騒音や損害について、様々な証拠が必要となるため、上記で述べたような証拠を集め、裁判所に提出する必要があります。
まとめ
本記事では、「隣人の騒音は違法?隣人の騒音が違法となるケースと法的対応について解説」と題して、解説しました。
- 隣人の騒音が違法となるか否かは「受忍限度」を超えたか否かで決する
- 「受忍限度」を超えているか否かの判断は音の大きさだけではなく、時間帯や継続性といった様々な事項を総合考慮して決する
- 騒音が気になる場合、様々な証拠を収集する必要がある
- 法的な対応の順序を意識する
隣人の騒音は、日々の生活に悪影響を及ぼします。
一方で、対応を間違えると近隣トラブルに発展しかねません。
そこで、隣人の騒音が気になる場合は、本記事で解説したことを参考に、適切に対処しましょう。
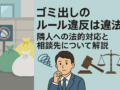
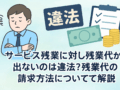
コメント