はじめに
アルバイト先から「明日から来なくていい」と言われ、急にクビにされ、「違法なのでは?」と思った経験や不安を抱えたことがあるかもしれません。
結論から言うと、アルバイトだからといって簡単にクビにできるわけではありません。
法律では、解雇には正当な理由が必要であり、不当な解雇は違法となることがあります。
そこで、本記事では、アルバイトでも知っておくべき解雇の要件と、理不尽にクビと言われた際の対処法を詳しく解説します。
アルバイトの解雇が認められる根拠
アルバイトの雇用契約が終了する要件は、無期契約の場合と有期契約の場合とで異なります。
そこで、それぞれの解雇が認められる要件を以下で解説します。
無期雇用の場合
まずは無期契約の場合についてです。
無期契約の解雇に関する基本ルールは、労働契約法16条に定められています。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
この条文を読むと、普通解雇が認められるためには、①解雇について客観的に合理的な理由があり、②解雇が社会通念上相当である必要があります。
文面を見ると、簡単に解雇ができそうな気がしますが、判例はこの要件を厳しく解釈しています。
例を挙げると、高知放送事件(最判昭52年1月31日判決)は、ラジオ放送局のアナウンサーが短期間で2度寝坊し、計15分間ラジオの放送ができなかった事案です。
この事案で、寝過ごしは故意ではなく過失であるなどと言った理由を挙げ、解雇が社会通念上相当とはいえないと判断されました。
また、会社の業績悪化といった、会社都合による解雇(整理解雇)については、解雇の有効性をさらに厳しく判断しています。
アルバイトであっても、労働契約法16条が適用されるため、アルバイトの解雇であっても、これらの要件を満たさなければ違法な解雇となります。
有期雇用の場合
有期雇用の場合の解雇については、無期雇用の場合とは異なり、労働契約法17条によって定められています。
使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
この条文を読むと、有期雇用のアルバイトを解雇するには、「やむを得ない事由」が存在する必要があります。
この「やむを得ない事由」は、上記の①解雇について客観的に合理的な理由があり、②解雇が社会通念上相当という要件よりも厳格に判断されます。
つまり、有期雇用の場合は無期雇用の場合よりも解雇のハードルが高くなっているといえ、より重大な事由がなければ解雇が違法となります。
本サイトでは、有期雇用と無期雇用の違いについても解説していますので、以下のリンクからご覧ください。
違法となる可能性が高い解雇の例
上記のような条文の解釈を踏まえると、次のようなケースは違法な解雇となる可能性が高いです。
- 店長の好みや人間関係などの感情的理由
- シフトに入れない週が続いたことを理由に「今後は不要」と言われた
- 数回の遅刻や無断欠勤
- 30日前までの解雇予告もしくは予告手当の支払いがない解雇
このように、重大な事由がないのにも関わらず解雇することは、労働契約法16条又は17条に違反し違法となります。
また、会社は解雇する場合、30日前までに予告が必要です(労基法20条)。
予告がなく、突然解雇された場合でも、予告手当の請求が可能です。
突然クビと言われたときの対処法
違法な解雇を受けた際には、以下のような対応をすることが望ましいです。
クビの理由を書面で求める
まず、解雇理由を文章で示すよう会社に対して求めましょう。
会社は労働者から請求があった場合、解雇理由証明書の交付義務がある(労基法22条1項)ため、書面の交付を受け、解雇の理由を詳しく知ることが有用であるといえます。
労働基準監督署や弁護士に相談
解雇の理由を見て違法なのではないかと考えた場合は、労基署や弁護士に相談することが有用です。
相談することにより、法的な見地から解雇の違法性を分析し、解決に向けて協力を得られる可能性があります。
まとめ
本記事では、「アルバイトをクビと言われた…これって違法?知っておくべき解雇のルールと対処法」と題してアルバイトをクビと言われた際の法的な問題や対処法について解説しました。
解雇はかなりハードルが高いことから、アルバイトをクビと言われた際には、冷静に理由を分析し、最適な行動をとるように心がけましょう。
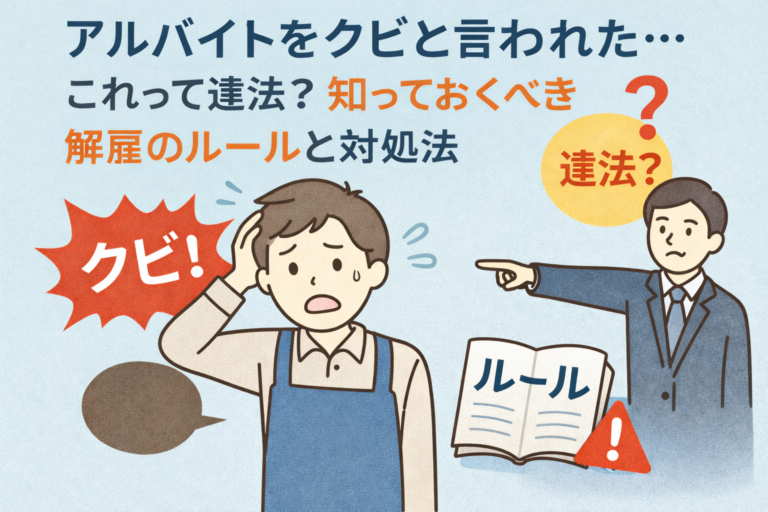
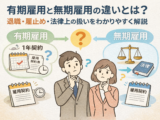
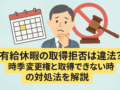
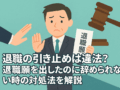
コメント